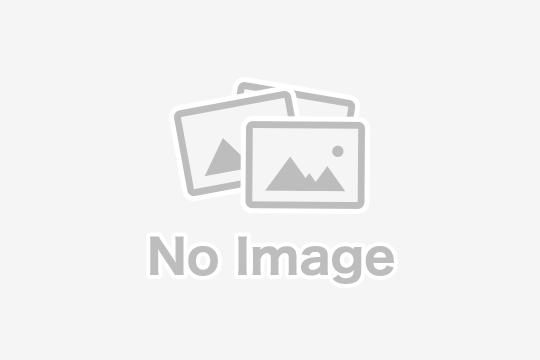抹茶が苦い理由と美味しい抹茶の見分け方|味の違いを徹底解説
「この抹茶、苦くて飲めない…」そんな経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
一方で、茶道教室で飲んだ抹茶は驚くほど美味しかった、という話もよく耳にします。
同じ抹茶なのに、なぜこれほど味に差があるのでしょうか。
抹茶の味を決める「覆い下栽培」
抹茶の味を決める最大の要因は「覆い下栽培」という特殊な栽培方法です。収穫前の3〜4週間、茶畑を黒い遮光ネットで覆い、意図的に日光を遮ります。
なぜわざわざ日光を遮るのでしょうか。実は、日光を遮ることで茶葉の成分が劇的に変化するのです。
通常、茶葉が日光を浴びると、旨味成分のテアニンが苦味成分のカテキンに変化します。遮光することでこの変化を防ぎ、旨味たっぷりで苦みの少ない茶葉に育てることができるのです。
この覆い下栽培が不十分だと、市販の安価な抹茶によくある苦みの強い味になってしまいます。
茶葉の品質による違い
最高級の抹茶には、その年最初の新芽「一番茶」の中でも特に上質な部分だけが使われます。新芽の先端部分は最もテアニンが豊富で、苦みが少なく甘味や旨味が際立ちます。
高級な抹茶では、熟練した職人が茎や古い葉を丁寧に取り除きます。一方、安価な抹茶ではこの選別作業が簡略化されているため、雑味や苦みが強くなりがちです。
石臼挽きと機械挽きの差
伝統的な石臼挽きは、ゆっくりと回転するため摩擦熱がほとんど発生しません。茶葉の風味成分は熱に弱いため、この低温での粉砕が抹茶の香りや味を保ちます。また、非常に細かく均一な粒子になるため、滑らかな口当たりを生み出します。
一方、機械で高速粉砕された抹茶は摩擦熱で風味が損なわれやすく、ざらつき感や苦みが目立つ仕上がりになってしまいます。
抹茶の等級と味の特徴
抹茶には明確な等級があります。最高級の「濃茶用」は旨味が強く苦みの少ないまろやかな味わい、「薄茶用」は適度な苦みと旨味のバランスが取れています。最も安価な「加工用」は苦みが強く、主にお菓子作りに使用されます。
美味しい抹茶の見分け方
良質な抹茶は鮮やかな翠緑色でつやがあり、粉は非常に細かくシルクのような滑らかさです。香りは青海苔のような爽やかさと、ほのかな甘い香りが特徴です。
実際に飲んでみると、最初に軽い苦みを感じた後、すぐに甘味や旨味が口に広がり、後味はすっきりしています。品質の劣る抹茶は苦みやえぐみが強く、後味も悪いことが多いです。
美味しく飲むコツ
抹茶を点てる際のお湯の温度は80〜85℃が理想的です。沸騰したお湯では苦みが強く出すぎ、温度が低すぎると旨味が十分に抽出されません。
薄茶なら茶杓1杯(約2グラム)に対してお湯60〜80ミリリットル、濃茶なら茶杯3〜4杯(約6〜8グラム)に対してお湯30ミリリットル程度が適量です。
保存は光、湿気、高温を避け、開封後は密閉容器に入れて冷蔵庫で保存し、早めに使い切ることが大切です。
まとめ
抹茶の味の違いは、覆い下栽培、茶葉の品質、製造方法、等級によって決まります。これらのポイントを理解することで、より良い抹茶選びができ、日本の伝統的な味わいを深く楽しむことができるでしょう。