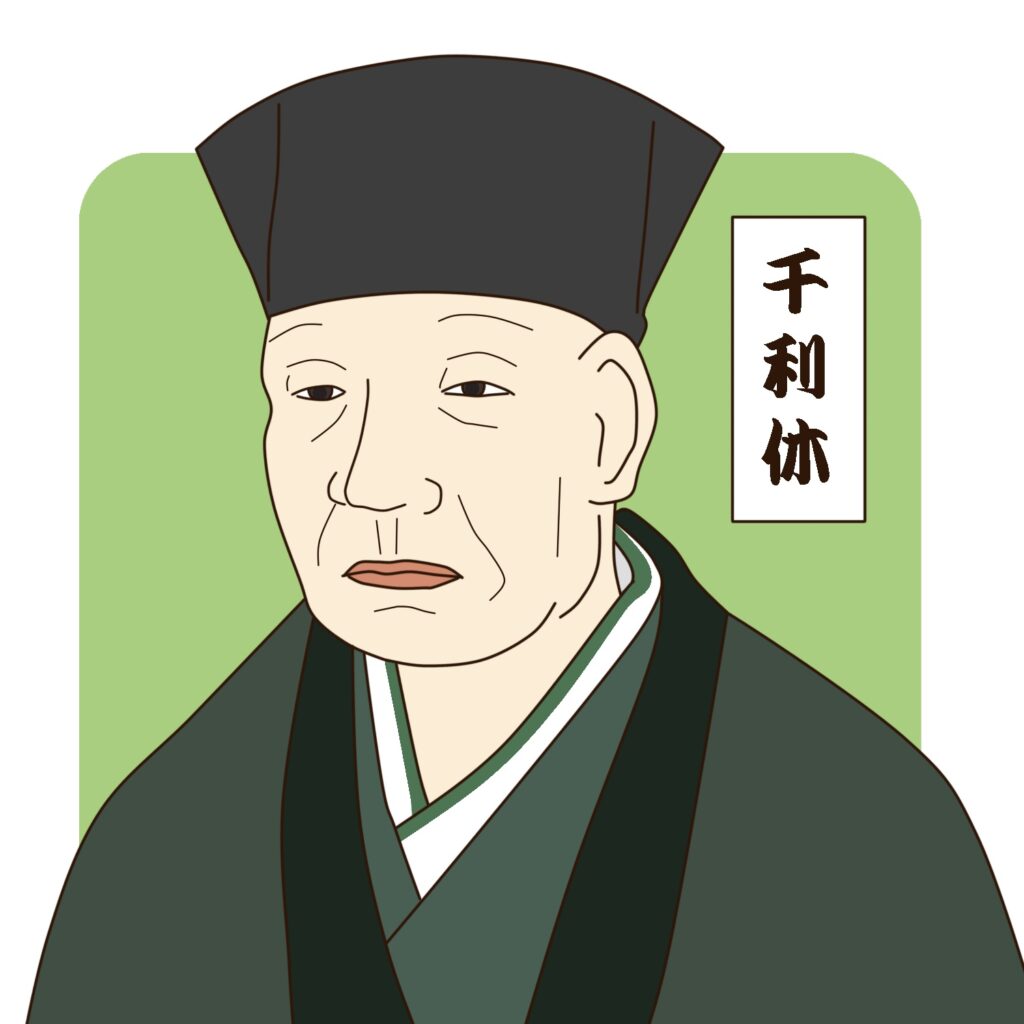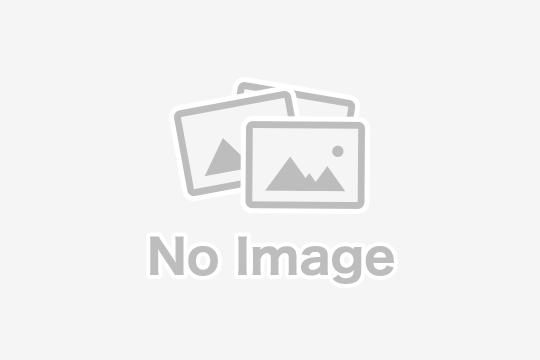「藤娘」──和菓子、歌舞伎、そして映画『国宝』でつながる日本文化
「藤娘」は、和菓子としても、歌舞伎舞踊の名作としても、そして2025年公開の映画『国宝』の中でも重要なモチーフとして登場し、日本文化の奥深さを象徴する存在です。
歌舞伎舞踊「藤娘」とは
歌舞伎舞踊「藤娘」は、1826年に江戸・中村座で初演された人気演目で、藤の花の精が娘の姿で現れ、恋心や女心を舞で表現します。
舞台には藤の花が天井から垂れ下がり、幻想的な雰囲気の中で女形役者が可憐に舞う姿が見どころです。
六代目尾上菊五郎が完成させたとされ、衣装や舞台美術、音楽など、歌舞伎の美の粋が詰まった作品として知られています。

映画『国宝』で描かれる「二人藤娘」
2025年公開の映画『国宝』(李相日監督、吉沢亮・横浜流星主演)は、歌舞伎の世界を舞台にした壮大な人間ドラマです。
任侠の家に生まれた主人公・喜久雄と、歌舞伎名門の御曹司・俊介が、芸の道で切磋琢磨しながら人生を歩む姿が描かれます。
この映画の大きな見どころの一つが、「二人藤娘」のシーンです。
物語の中で、主人公二人が舞台で「藤娘」を共演する場面があり、伝統的な一人舞踊ではなく、二人で演じることで、彼らの対照的な個性や関係性、そして芸にかける情熱が鮮やかに浮かび上がります。
天井から藤の花が下がり、二人の藤娘が左右から現れる演出は、映画でも非常に印象的に描かれています。
また、映画『国宝』では「二人道成寺」や「曽根崎心中」など、他の歌舞伎演目も登場し、歌舞伎の美しさや厳しさ、そして芸の世界の人間ドラマがリアルに表現されています。
和菓子「藤娘」と文化的つながり
和菓子の世界でも「藤娘」という名前の菓子があり、春の季節を感じさせる美しい意匠で作られています。
藤の花を模した見た目や、上品な味わいが特徴で、茶道の席でもよく用いられています。
日本の伝統文化では、季節の移ろいを和菓子に託して表現し、茶席での会話やおもてなしに彩りを添えています。
文化的な広がりと意義
和菓子「藤娘」は、その名前や意匠が歌舞伎舞踊「藤娘」に由来することが多く、茶道の席でこの和菓子をいただくことは、伝統芸能や日本文化への敬意を表す意味も込められています。
さらに、映画『国宝』で「二人藤娘」のシーンが描かれたことで、現代に生きる私たちも、和菓子・舞踊・映画を通して「藤娘」というモチーフが持つ文化的な広がりや奥行きを体感できるのです。
参考文献・出典
1. 東洋経済オンライン「映画≪国宝≫に歌舞伎俳優も驚嘆!」
1. T JAPAN「吉沢亮と横浜流星が熱演の『国宝』」
1. 読売新聞「吉沢亮と横浜流星が女形演じるヒット映画『国宝』」
1. エキサイトブログ「映画『国宝』鑑賞」
1. X Knowledge「映画『国宝』を味わい尽くしたい人は必見!」
1. Amebaブログ「つれづれそ2396.映画『国宝』(2)藤娘・文様 など」